Azure Diary
平成二十六年 葉月
■2014/08/12 火
お盆休み、ではないのだが今日と明日は休暇にした。今夜はペルセウス座流星群の極大日になる。なので今年も向かう。日本一星空に近い場所へ。ほぼ満月だけど、まぁ地上で見るよりはよかろう。
昼まで寝て昼過ぎに出発。去年登ってもう御殿場口からは登らない、と言っていたにも関わらず一年経てばその辛さも忘れるもので今年も再び御殿場口から登ることに。御殿場市内で食べ物やホッカイロなど装備の最終調整。ただ、御殿場市街に入った時点で大雨。雲を抜けることを期待して御殿場登山口まで上がってみたけれど、やはり土砂降り。そのうえ強風。登山口で情報収集すると、今日はこの天候により御殿場口から登ったのも15組くらい。他の登山口もツアーは軒並み中止のよう。コンディションは過去最悪。
情報収集と天気予報確認で一時間ほど。これは登っても楽しくないが、天気予報では雨は日付が変わる頃までで明日は晴天なので登ることに。ただこの強風だと山頂の体感気温は冬だろうと、装備を切り替え。リュックから詰めていたカッパを出して、雨具兼用の防寒ジャケットに切り替える。
そうしてさて、登ろうか、という時に登山道入り口で県の腕章をした人たちに声をかけられる。「え、登るんですか。あ、では協力してくれませんか」と。聞くと登山者にGPSを受信して位置を記録する装置を持って登ってもらうことで登山者の動向調査をしているのだと。快諾しリュックの中にGPS受信機(GPSロガー)を入れる。降りてきたらまたここで回収しますんで、とのこと。何か背中に発信機を付けられたウミガメの気分。
18時過ぎに土砂降りの御殿場口を出発。体のバランスが崩れるほどの強風と横殴りの雨…いや、タコ殴りの雨の中を登ってゆく。今回は雨と強風、そして低温のため、あまり早く昇ってしまうと山頂で動かずに朝まで待つのが辛いので、できるだけゆっくり登って体を動かし続け日の出の時間くらいに丁度山頂に着くようペースを調整する。元々人が少ない御殿場口なうえ、この天気なので山頂付近でラッシュに巻き込まれることもない。
日付が変わる前に御殿場口6合目、標高2800m付近に到着。途中で雨雲を抜け、ようやく雨も止んだ。ただ、上空にはまだ雲があり、星はその隙間からちらほら覗くだけ。しかも満月で空も雲も明るいので、流れ星も本当にちらほらと流れるだけ。その上、雨は止んでも風が強いのでなかなか上を向く余裕もなく、今回は全く星を見るのには向かなかった。
■2014/08/13 水
日付が変わったころ標高3000m地点に到着。本当に気温が低く、あまり長く休んでも体が冷えるだけなので、ここからは更にゆっくりと体だけは動かし続けるように登ってゆく。山頂までの道のりで何回か、ヘッドライトの光の中を雪が舞ったような気がしたけれど、それが本当に雪なのかどうかは強風のため確認できなかった。
山頂に着く前に東雲。地平が青く明るくなり始める。そうしてそのまま山頂へ。馬の背を登り剣が峰へ。朝4時半頃に、昨年そこで日の出待機していたものの雲で日の出が見えなかった最高地点の三角点に到着する。日の出までおよそ20分ほどなのだけど、登山口で聞いたとおりツアーの人たちもいなく人疎らな山頂。
三角点の近くにある本当に日本最高地点の岩の上に立ち日の出を迎える。雲海で日の出時刻からやや遅れたけれど、同じ位置に立つ人はいなかったので、今日。2014年8月13日の朝は、自分が日本で最初に迎えたことになる。光栄。日の出の瞬間は手を合わせ、日が昇った後で写真を撮る。

ただ、雲海がなければこの場所からだと日の出の位置が火口東側の尾根の影になりそうなので、実は普段は最高地点イコール日の出が一番早い地点、ではないのかも知れない。
明るくなってから周囲を見て、改めて驚く。今回で七回目になるけれど、こんなにガラガラな山頂もまた、初めてのこと。普段は人が入れ替わり立ち替わり記念写真を撮っているので人の切れ目がない最高峰の碑も今日は誰もおらずぽつんとしている。

日の出待機で体が冷えたので、日が昇ってからは御来光でしばらく日向ぼっこ。山頂の気温は体感温度だけではなく実際の気温もマイナスになっていたようで、山頂の水たまりには薄氷が張っていた。

写真を撮ってからパリパリと真夏の氷踏み。これは朝イチに見つけた人の特権。
他にも、山頂周囲を歩いていたらあちこち霜柱が立っていたり。

つららが下がっていたり。

と、真夏の冬を堪能した。そういえばつららって、こちらの平地では真冬でも見なかったような気がする。最後に見たのはいつだっただろう。
少し温まってから剣が峰を降り、お鉢を巡る。影富士が綺麗に見える。

影富士の山頂に傘が被っているように見えるが、これは山頂に雲がかかっているからではなく。影富士が伸びている反対側の上空に、今日のように風が強い日の山頂脇に現れるこの「吊るし雲」が浮いているから。

吊るし雲も、麓からは見たことはよくあったけれど、こうして山頂から見るのは初めてだった。この高さから見ると巨大なUFOみたいだ。今回はこれまでで最も悪コンディションの登山だったけれど、そのおかげで今回初めて見ることができたものも多かったと思う。富士登山7回目なんて、まだまだ初心者。ということなのかも知れない。
お鉢(火口)を一周して下山開始。そういえば。そんな冬のような山頂だったけれど、山頂付近の岩肌には苔以外にも緑があり、花を咲かせていた。

大きめなハコベのような花。名前は判らなかったので、写真を撮ってきて後で調べたところ、この花は「岩爪草(イワツメクサ)」だった。写真の花はほぼ山頂に咲いていたので、この花が間違いなく日本一高い所に咲いている花。

これが本当の高嶺の花だね。
あとは青空の下をひたすら楽しい富士下山。下山の人の少なさとは対照的に、天候が回復してから山小屋を出てきた人や早朝から登り始めてきた人が登山道に増えてくる。標高が下がって来ると先ほどの岩爪草の姿が見えなくなり、砂礫に根付くこのオンタデが目立つようになる。

オンタデ、というのは漢字で書くと「御蓼」で。長野県にある3000m超の独立峰、御嶽山にその群落があることがその名前の由来になったのだそう。
山小屋で休憩中の登山者や、富士山が好きで山小屋でアルバイトをしている、という高校生の女の子とおしゃべりしたりしながらの下山。そういえば、そうした人と話をしていてちょっと相手にびっくりされたのが、自分の足元だった。今回、いままで登山に使っていた靴がさすがにもう駄目になってきたので買い換えた。ただし、登山靴というのはかなり高価なので、これから何回登るかわからない山登りのために買うのもちょっと。なので、今回は使い捨てのつもりでこの究極の2000円シューズで登っていた。

いや、シューズですらなく地下足袋(足首に巻いているのは反射テープ。ふくらはぎに巻いているのは脚絆)なのだが。「それで登ったんですか!?」と驚かれる方が多かったのだけど、地下足袋はふくらはぎまで丈があるので、くるぶしまで埋まるような砂地がメインの御殿場口でも砂が入らないし、底は薄めだが岩場も少ないので実用としては充分だった。御殿場口の20キロ近くを登って降りてで破れや底の剥がれもなく、さすが地下足袋という感じ。
ただし、地下足袋登山はネタでやったわけではなく。もし読まれた方に誤解ないように書いておくと、一般の方に地下足袋はお勧めしない。まず登山靴のように足首が固定されないので、慣れていないと捻りによる怪我をする可能性があること。爪先が固くないので岩にぶつけても指先が護られないこと。あと、底の薄い地下足袋は登山靴や運動靴のような靴底のクッション効果が皆無なので、歩き方を知らないと砂礫と岩場の登山道を長距離歩くことは難しく、足を壊す可能性もあるので。
(注)自分の場合はもう長年、普段の10キロ以上の駆け足を、さすがに地下足袋ではないけれど運動靴ではなく底のクッションがない薄い靴(最近でいうベアフットランニングシューズ)で走るトレーニングをしているからこそ地下足袋での登山も可能、ということなので、そういう備えのない方は決して真似をしないようにお願いします(かかとから着地する歩き方ではまず無理。地下足袋による富士登山は少なくとも10キロのランニングを、かかとから足を付かない「つま先着地」のみで無理なく走り切れるくらいにならないと厳しいと思います)。
と、話を戻して。その後、宝永山に立ち寄り、御殿場口名物の大砂走を駆け下りて(スマホのGPSで測ったら3.5kmの距離をを12分で文字通り駆け下りていた)帰りはあっという間に下山。登山道入口で県の腕章をつけた人を探して、登る時に渡されたGPSロガーを返納する。
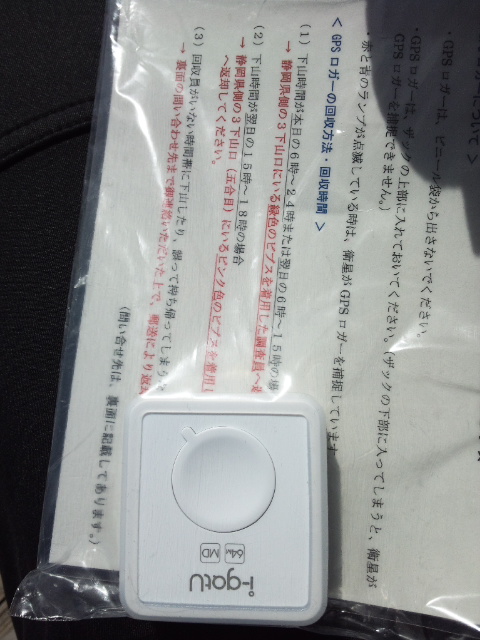
県の人にも「ああ、あの地下足袋の人」と憶えられていたらしい。この記録がお役に立てたらいいのだけど(その後さらに5枚ほどのアンケートに協力することになった)。
アンケートを書いているとその項目に、昨年度から始まった「富士山保全協力金」についての項目があった。そこで思い出した。この実質入山料である制度は昨年度から始まったのだけど、1000円を払う代わりに記念品がもらえる、とのことで昨年度もそれが欲しかった(何回も登っているけれど、登った、という記念になるものがこれまで無かったので)のだけど。昨年度はこの御殿場口は「登山者が少ないので集めていない」とのことで、払うことも貰うこともできなかったのだ。
なので今回こそは、と。県の人に「これどこで払うの」と訊いて、窓口を教えてもらう。で、昨日夜登ったけど入山の時に払えなかったから、と行ってみたら窓口の人が「いや昨日はあの天気でしたし夜は窓口閉めてたもので。あ、登る時徴収できなかったのでいま無理に払う必要はないですよ」とのこと。なんだ、意外と緩い制度だな、と思いつつ、いや俺はその記念品が欲しいので!と遠慮がちな窓口の人に1000円払って缶バッチと冊子とシールを貰ってきた。
登山口から市内へ降りて、温泉へ。いつもはその後「とらや工房」の氷あんみつ、なのだけど。今回はさすがにもう疲れてしまったので真っ直ぐ帰宅。流れ星は散々だったけれど、悪天候ゆえ普段は見られない富士山の姿を見られた富士登山、だった。果たして次はあるのだろうか。
■2014/08/21 木
日中は蝉がわしわしと鳴いている。けれど、夜にはリリリと鈴虫の声が聞こえるようになった。お盆を過ぎて少し秋めいてきた感じのする夜。この国の季節は四つの季節に分けられるけれど、見方を変えると概ね二つに分けられるのだと思う。それは春と夏の「南からやってくる季節」と、秋と冬の「北からやってくる季節」。今は大体、その二つの季節の境目に、ちょうどあたるのだと思う。
間もなく秋。暑さもなく、寒さもなく、心地よい季節。そんな季節がずっと続けばよさそうなものだけど、恐らくは。そんな心地よい季節が一年の間ずっと続いていたら、その季節の心地よさというものに気付くことはないのだろうと思う。秋の涼しさの心地よさ。それは耐えがたい夏の暑さがあったからこそのもの。
ひとつひとつの季節は、けっしてひとつだけでは成り立たない。それぞれ違う四つの季節があってこそ、それぞれの季節が他のそれぞれの季節を魅力的にする。異質を排除するのではなく、異質同士が異質のままひとつにまとまり、それぞれから他のそれぞれをより魅力的にすること。四季はまるで、調和の見本。